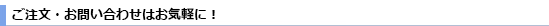- はんこ屋さんスクウェア
- 創業20年の3店舗の実績と紹介
- 即日TOP便サービス(翌日到着)
- 印鑑の書体確認サービス
- 文字校正(ゴム印・名刺)サービス
- 安心の印鑑10年間保証
- お客様レビュー(ご感想)
- 印鑑ランキングBEST10

- ご注文方法(お買い物の流れ)
- ショッピングガイド
( お支払い・ 送料・ お届け方法) - 印鑑の選び方について
(材質/サイズ/書体) - 直営店3店舗から見た傾向
- 旧字のお客様
- 印鑑百科事典(個人編)
- 印鑑百科事典(法人編)
- FAX注文
- 大口注文お問い合わせ
- よくあるご質問(Q&A)
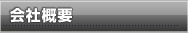
|
|
|
|
|
|
|
|
|


- 会社 実印(代表者印)
- 会社 銀行印
- 会社 角印
- 役職印(理事・会長・事務等)
- 契約印(領収・請求・契約等)
- 職印[先生印]
(弁護士・弁理士・税理士等) - 会社設立応援2点セット
- 会社設立応援3点セット
- 会社設立完全3点セット
- 会社設立完全4点セット



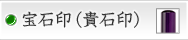

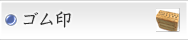
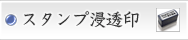





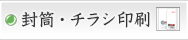
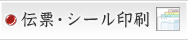
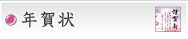

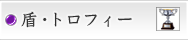
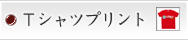
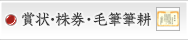

はんこ屋さんスクウェアは、SSL通信中の情報の暗号化、第三者の盗聴、改ざん、成りすましなどから保護される事を認証する、ベリサインのセキュア。サーバーIDをカートシステム会社から間接的に取得しております。

経済産業省 ・ 環境省認定
特定国際種 事業社番号
T-3-13-00111
T-3-13-00112
T-3-14-00102
[全省庁統一資格]
業者コード 0000075656
事務用品類
業者コード 0000063219
フォーム印刷/その他印刷類

正会員 会員番号C0143155
○当店では定期的に下記エリア・駅にてチラシ配り、ポスト投函、新聞折込みチラシを行っております。
[虎ノ門店]
[横浜戸部店]
[虎ノ門店]
[横浜戸部店]
【虎ノ門店】
虎ノ門 新橋 溜池山王 赤坂 青山
赤坂見附 霞が関 神谷町 日比谷
内幸町 御成門 六本木 麻布 麹町
大門 芝 三田 銀座 浜松町 田町
有楽町
【横浜戸部店】
横浜 戸部 日ノ出町 黄金町 井土ヶ谷
上大岡 東神奈川 反町 菊名 高島町
みなとみらい 馬車道 桜木町 関内 石川町
吉野町 天王町 星川 保土ヶ谷 戸塚
鶴見(西区・中区・南区・保土ヶ谷区・神奈川区)
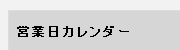
営業カレンダー
| 今日 | |
| 定休日 |
[店舗営業時間]
平日:10時~19時
(休:土・日・祝)
[ネットショップ営業時間]
平日:10時~15時
(休:土・日・祝)
メディア掲載 記事全文
印章/スタンプ/軽印刷の専門誌 以下、記事全文 株式会社エム・ホワイトラビット(はんこ屋さんスクウェア) 東京三代の家に生まれたから、地方のいろんな町を訪ねる旅行が楽しみだった。家が貧しいため安い旅行だったが、それでも両親に連れられて訪れた見知らぬ町々の景色は少年の目を輝かせた。
旅行業界で働こう、鈴木 剛志 氏がそう決めたのは中学生の時。数々の楽しい旅行の思い出がそう決意させた。
念願かなって、大学卒業後、大手百貨店の旅行事業部に就職したが、少年の夢は長く続かなかった。
十年間、旅行販売で汗を流したがバブル崩壊で旅行事業が縮小。好きな仕事が出来ないのならと会社を飛びだした鈴木氏は、当時まだ出来立ての印章フランチャイズチェーン「はんこ屋さん21」の門を叩いた。
旅行業では、飛び込み営業から、企画、見積もり、精算まで全てを一人でこなしていたため、個人事業主としてのスキルは身に付いていた。旅行業と印章店、仕事の内容に関連性はないように思うが、「今振り返れば、相通じる面も多い」と鈴木氏は言う。
「旅行って体験してしまえば消しゴムでは消せない商品。だから接客も一期一会、一つ一つの案件を大切にしなければなりません。ハンコも同じですよね。人生の節目節目に使うアイテムだからいい加減に売ってはいけない。やっぱり一期一会の商売なんですよ」。
「印章店が『待ち』の商売なら自分は待たずに攻める。チラシは撒けば撒くほどお客が来る」 自分の店を持つまでの研修期間中、鈴木 氏は神奈川県下の「はんこ屋さん21」の開店支援に駆り出された。
開店前の仕掛けとして、ポスティングと手配りでチラシを五千枚撒いた。その結果、オープン初日は1日で象牙七十本、約八十万円を売り上げた。二日目は四十本の注文。アルバイト二人が徹夜作業で木口の仕上げをした。
「すごい。ハンコ屋ってこんなに儲かるのか」。
……この時の原体験が、チラシ戦略に重きを置く鈴木 氏のハンコ屋哲学を形成したと言っていい。
その三ヶ月後の96年5月21日。待望の自分の店がオープンする。
場所は東京都港区虎ノ門。霞ヶ関の官庁群に臨むビジネス街だ。この場所を選んだ理由は、人口密度の高さと、旅行業時代から培った法人廻りのノウハウが活かせる場所をと考えたから。しかし場所がいいぶん、投資も大きい。開店のための借金は四千万円に膨らんだ。
店と言っても、更地の土地にプレハブ小屋を建てて什器二台を置いただけ。後に、現在のビル一階のテナントに移るまで、冬は隙間風が寒かった。
ところが、この粗末な店が脅威の売上げを叩き出す。オープン月の5月度の売上げは、二週間足らずにもかかわらず二百十万円。その後も勢いは衰えず、9月度に三百万を越え10月度は四百五十万円に達し、ついに21チェーン内で全国一位となる。
ハンコ屋は儲かる……鈴木 社長は一年後に横浜戸部店を、さらにその一年半後、東京赤坂にも姉妹店をオープン。FC加盟店でありながら自己資本で21を三店舗展開した。現在は、鈴木氏が社長を務める法人、エム・ホワイトラビットが三店舗を統括している。
今もその売上げは衰えることなく、虎ノ門店の通常月で約七百~八百万円、年賀状の絡む年末になると千三百万円を売り上げる。路面店単独の売上げとしては目を見張る数字だ。赤坂店でも通常月で約六百万円、横浜戸部店で約四百万円が当たり前の売上げだという。
この機関車のような売上げの燃料になっているのがチラシ、それもポスティングや手撒きのゲリラ的な広告宣伝だと鈴木氏は言う。
「まずお店にきて貰うためには広告宣伝が重要です。ただし新聞折込チラシは都心部では費用対効果が悪い。一過性で終わってしまって効き目がないんです。それよりも手撒きとポスティング。配れば配るほどお客は来てくれる」。
鈴木氏はプレハブ小屋時代から自らそれを実践してきた。朝5時に起きて虎ノ門駅の出口に立ち、二時間かけてチラシを手配りする。それから店を開け、さらに二時間、周辺の事業所をポスティングして回る……オープンから五年間、日曜日以外一日も欠かさず計四時間にわたるチラシ撒きを続けた。
「私は待つことが出来なかったから……」鈴木 氏は当時を振り返ってそう笑う。印章店は「待ちの商売」だから難しいと知人に言われ、それなら自分は待たずに攻めようと考えたのだという。
その成果が如実に現れたのは郵政省(現・郵政公社)の名刺受注だった。
虎ノ門店オープンから一年ほど経った土砂降りの朝、鈴木氏は郵政省の前でチラシを配っていた。悪天候が災いしてチラシを受け取ってくれたのはたったの三人だったが、その後の数週間で郵政関係の名刺の注文は千件を越えた。役人は個人負担で名刺を作る、だから安い早い近い店の情報がクチコミで広がったのだ。以後、同店では官庁をターゲットにした手撒きチラシに力を入れはじめる。
「お客様の立場に立たず、営利目的を最優先して、プロの店員として接すること」 これだけだと、鈴木氏が新規客獲得だけ血眼になっているように見えるがそうではない。それは、虎ノ門店のリピート率(再来店率)が95%にものぼることが証明している。
まず一枚のチラシを受け取ったお客が店の存在を知ってくれる。そして来店してくれれば、店では丁寧な接客で確かな商品を提供する、それがお客様満足となり再来店に繋がる……そのサイクルの最初のきっかけがチラシ撒きというわけだ。
また、チラシ撒きは集客だけでなく、接客技術の向上にも繋がると鈴木 氏は言う。
「極端な例えをすると、店に入ってきた瞬間にその人が何を買いに来たか分かるようになる。毎朝、チラシ撒きで道行く人達を見てると、この人は元気だな、この人は疲れているな、もしかして足がお悪いのかな……というようなことが見えてくる。そうした観察眼が接客で生きる。疲れた足取りの方にはまず席を勧めたりと、真心を込めた接客が出来るようになるんです」。
チラシ撒き以外に鈴木氏が信条とするのは、「お客の立場に立たない」ということ。
例えば、エム・ホワイトラビットの新入社員に対し、鈴木社長はいつもこのように訓示する。
「お客様の立場に立たず、営利目的を最優先して、プロの店員として接すること」。
「営利を最優先」では前段の「お客様満足」と矛盾するのでは?記者がそう詰め寄ると、鈴木氏は、「じゃあ、真のお客様満足とはなんでしょうか?」と投げかけた。
「例えば、最近もてはやされているインターネット通販では、店の入れ替わりが激しい。売った後は知らん顔で店を畳んでしまうようなやり方がお客様への一番の裏切りではないでしょうか。印章は一生使い続ける商品ですから、販売後、長期間サポートするのも店の責任。そこに店があり続けること、会社が存続することが結果的にお客様の満足になる。きれい事だけでなく、そういった長期の経営視点を持って店に立たなければならないのです」。
「売り方が古くなる、新しいものを開発しない……そう考えてFCは5年でやめようと決めていた」 だから、売り手がお客に同化して、安いものを手頃に販売することで安住してはならない、店の利益を考えよと教育しているのだという。
営利追求と顧客満足が相反しない具体例がある。同社では、「ハンコを買いに来たお客にハンコを売るな。名刺を買いに来たお客に名刺を売るな」というスローガンがある。そのココロは、
「ハンを買いに来たお客がハンを買うのは当たり前。店員が当たり前で終わったらダメなんです。ハン以外に名刺も出来ますよ、会社設立ですか?封筒はどうですか?ゴム印も早いですよ……と他の商品もどんどん提案する。お客様にしても、一軒の店で複数の用事が済めば便利。知らずにあちこちの店を回らせることを考えたら、うちの扱い商品を全て紹介しないのはお客様にとって罪なんです」(鈴木氏)。
そういった独自の哲学で快進撃を続けてきた同社だが、05年10月に「はんこ屋さん21」のFC本部と契約を解除し、自社独自のショップブランド「はんこ屋さんスクウェア」を立ち上げる。虎ノ門、赤坂、横浜戸部の三店一斉に21の看板を下ろし、新しい屋号に掛け替えた。
なぜ、鈴木 社長はこれほど順調だった列車から突然降りてしまったのだろうか。
「突然のように見えるかも知れませんが、実は21に加盟した頃から五年でやめようと決めていたんです。それが少し長びいただけ。もともと売り方が古くなる、新しいものを開発しないといった理由で『FC五年衰退論』を持論にしていましたが、現実にそれが見えてきた。加えて、出店テリトリーの基準が緩くなってきてうちの周辺への出店も増えたため、当初の脱退計画を実行に移しただけなんです」(鈴木社長)。
同社では現在、全店をテレビ電話で結んだ遠隔接客システムを導入。店員で分からない商品知識や納期の確認などをモニター画面を通しておこなうシステムを整備した。印章業界では初の試みである。
さらにインターネット通販とも連動して、ITを積極的に活用した新しい印章の販売方法を模索している。
「チラシ撒きは畑を耕すのと同じです。雨の日も風の日も畑を耕す、そこには私の生活や真心が全てこもっている。それをきれい事で売るのではなく、会社が存続するような仕組みと最新の技術を取り入れる。最終的にそれがお客様の満足になれば最高だと思っています」。
(終)
|

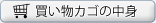
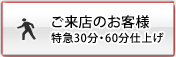
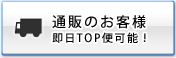



![[虎ノ門店]](https://www.hankoya21.co.jp/pic-labo/glo_side_46.jpg)
![[横浜戸部店]](https://www.hankoya21.co.jp/pic-labo/glo_side_47.jpg)
![[虎ノ門店]](https://www.hankoya21.co.jp/pic-labo/glo_side_48.jpg)
![[横浜戸部店]](https://www.hankoya21.co.jp/pic-labo/glo_side_49.jpg)